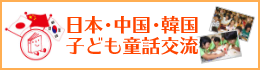安全・安心な助成活動の実施について

-
子どもの健全な育成を願って企画された活動でも、安全上の注意を怠ると大きな事故につながりかねません。
安心して子どもたちが活動に参加できるよう、以下の例を参考に、安全管理・健康管理対策をしっかり行いましょう。
事前の準備
1.日程・スタッフ体制の設定
詰め込み過ぎた日程だと時間が押しがちです。余裕のないスケジュールは焦りにつながり、事故へとつながります。余裕をもった設定をしましょう。
スタッフは各プログラムでのそれぞれの役割を明確にし、安全に活動を実施できる体制づくりをしましょう。 必要に応じて外部機関との連携も視野に入れておきましょう。特に最寄の医療機関は、事前に複数個所リストアップしておくことが大切です。
2.活動場所の下見
実際の活動を行う場所の下見を行うことで、危ない場所の事前確認や、想定できる危険の予知ができます。 どこが危険なのか、どうし たら危険を防げるのか、危険を回避するための対策を、引率者で連携しながら行ってください。
施設を訪れる場合、下見の際に職員の方と打合せを行っておくことで、より綿密な対策を立てることができます。
例:交流を目的とする活動「幼児との遊び・ふれあい体験」
<下見結果>
幼児の身長だと頭部に当たる出っ張りがあったため、その箇所には立ち入らないようにすることとした。会場が広く、走り回る子がでる可能性があるため、活動始めに注意喚起をする必要ができた。
例:科学体験活動「星空観察を通した自然科学ワークショップ」
<下見結果>
予定している時間帯は、外灯も少なく、予想していた以上に足元が暗かった。段差がある箇所では声掛けする、子どもたちにもライトを持参させ、足元を照らせるようにするなど、対策が必要なことが分かった。
例:自然体験活動「森の中でオリエンテーリングを行う活動」
<下見結果>
分かれ道があり、参加者がコースを外れる危険があったため、人を配置しておく必要が分かった。 途中急斜面があり、転倒の恐れがある。参加者に配付する地図に注意書きをするとともに、安全に歩く方法を周知する必要ができた。
3.用具・持ち物の決定
活動に必要な用具・物品は事前に確認し、余裕をもって準備しましょう。
また、指導者側が用意する用具や装備は必ず、保守点検しておきましょう。
4.活動の中で起こり得ることを想定しておく
活動のプログラム内で起こり得る危険を想定しておき、回避できるように事前準備をしておきましょう。
また、どんなに事前に準備しても、事故やケガは起こり得るものです。そうなった場合に備えた準備もしておくことで、迅速な対応を取ることができます。
例:自然体験活動「川でのフィールドワーク活動」
参加者がけがをすることが想定できるため、救急セットを用意する。緊急車両の手配と搬送経路の確認・医療機関の確認を行っておく。
例:科学体験活動「科学薬品を使って実験をする活動」
参加者が誤って薬品をこぼしてしまうことが考えらえるため、ゴーグルや白衣を着用した上で実験を行う。
例:交流を目的とする活動「郷土料理を通した異世代交流活動」
参加者がアレルギーを持っている食材を食べないように、申し込み時にアレルギーの有無・程度を確認し、団体内で事前に共有しておくとともに、個別対応が取れる体制をつくっておく。
この他にも、
- 緊急時の避難方法、避難経路の確認
- 事前の活動場所の環境整備
など、様々なことが考えられます 。
5.天候判断
屋外の活動の場合、当日の天候によっては活動の実施が困難となる場合があります。
雨天時、どの程度であれば活動を実施するのか、延期とするのか、中止とするのか、事前に打ち合わせておくことで、迅速な対応を取ることができます。
必要に応じて、雨天時用のプログラムを用意しておくとよいです。
当日の対応
1.参加者の情報を得る
参加者の基本情報(氏名・年齢・連絡先など)
申し込み時や受付時に記録しておくと、緊急時の対応が取りやすくなります。
健康状態(体調の確認、体温チェックなど)
軽度の症状だったものが、活動の途中で悪くなる可能性もありますし、症状によっては他の参加者に影響する場合もあります。
体調状況を知っておくことで、活動中も意識を向けて配慮することができます。
キャンプ等、長期の活動の場合、毎日の健康状態を記録に残しておきましょう。
2.参加者の状態確認
体調の変化や安全へのは勿論ですが、様々な関わり合いや活動の中で、心の痛手やダメージを受ける参加者もいますので、心の安全にも配慮しましょう。
参加者同士の気持ちを伝え合える「雰囲気づくり」を心がけましょう。
また、参加者の活動への意欲や意識が低下している場合、思わぬ事故やケガにつながることがあります。 体力的な疲れや、不安感、注意力の散漫など、理由は様々に考えられます。必要に応じて、休憩や動機付け、注意喚起をしてきましょう。
3.事故・ケガにであった時
どんなに注意してもやはり事故が起きることはあります。その場合、初動が被害者を救済できるかどうかを左右します。最も気を付けなければならない3点を心得ましょう。
- 冷静になる 適正な判断ができなくなると、場合によっては被害を拡大してしまう恐れがあります。
- 自分自身の安全管理をする 二次災害を防ぐためにも、十分に注意が必要です。
- 被害者以外の人たちの安全管理をする 被害者の方はもちろんですが、それ以外の人たちの安全管理を十分に徹底したうえで救助に向かう必要があります。
4.記録をとっておく
事故発生の日・場所、処置の内容、けが人の名前・住所、事故の状況と程度など、必ず記録として残しておき、 病院や保護者への説明時や保険会社への報告の際に必要となります。できるだけ詳細に書いておきましょう。
事後の対応
1.参加者・保護者への連絡
事故・傷害の負傷者やその保護者には誠意ある対応が不可欠です。事故・傷害発生の一報は、保護者にできるだけ速く・正確に伝えることが重要です。
事故の際は、他の参加者や保護者へも同様に速く・正確に伝えるとともに、プライバシーに配慮し、誤解を招かないよう、正確な表現に努めましょう。
感染症の発生が後日分かった場合、参加者全員への連絡、使用した会場への報告等が必要となります。把握した内容を正確に伝え、いたずらに不安をあおらない様努めましょう。
2.保険について
活動中に起こることが予想される様々な事故によるスタッフまたは参加者の傷害や賠償責任を考え、団体で保険に加入したり、参加者へ保険の加入を義務付ける等、対策を講じておくとよいです。
感染症対策について
活動時は活動の実態を考慮した上で、基本的な感染防止等の対策を徹底し、感染防止へ努めましょう。
1.感染防止対策例

-
- マスクの常時着用
- 大声を出さない
- こまめな手洗い・消毒の奨励
- 会場のこまめな換気
- 密集の回避
- 検温の実施
- 参加者情報の把握(可能な限り予約制、あるいは受付時に連絡先の把握)
2.感染症対策に関する調査報告
文部科学省の調査研究結果等及び国立青少年教育施設における感染症防止対策ガイドライン、
感染防止対策事例等を集約した資料となっています。感染防止対策にご活用ください。
〇文部科学省
〇国立青少年教育振興機構